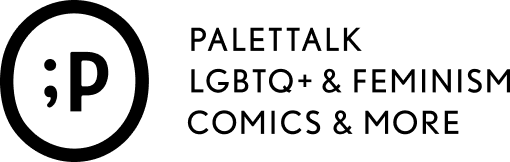『リトル・ガール』

「ただ、わたしとして生きる」ことを社会から受け入れられ難いという人はたくさんいる。
映画『リトル・ガール』の主人公、7歳のサシャもそのひとりだ。フランス北部で生まれたサシャは、生まれたときに男の子であると割り当てられたが、2歳を過ぎたころから、自分は女の子であると訴えてきた。
この映画はサシャとその母、そして家族を追いかけたドキュメンタリーで、実際にこのポスターに写っている少女(リトル・ガール)が、サシャである。

この記事では、2021年11月19日に上映が開始された映画『リトル・ガール』を紹介したい。
セバスチャン・リフシッツ監督がメガホンをとった本作は、2020年ベルリン国際映画祭で上映後、様々な映画賞を獲得し続けている。また、劇場の封鎖されたフランスでは、同年12月にTV局ARTEにて放送。視聴者数1,375,000人、その年のドキュメンタリーとしては最高視聴率(5.7%)を獲得。オンラインでは28万回以上の再生数を記録し、大きな反響を呼んだ(映画『リトル・ガール』公式サイトより)。
サシャは他の7歳の女の子と同じように学校へスカートをはいて通いたい気持ちや、バレエ教室で他の女の子と同じ衣装を着たい気持ちを持っている。それはもちろん誰かを傷つけるような自分勝手な欲望ではなく、等身大で映し出される小さな少女の本当に純粋で素朴な、持っていてあたり前の願いであることを多くの観客は感じ取るだろう。
そして幾度となくそんな彼女の小さな願いは、学校の対応や大人たちの態度によって打ち砕かれていく。子どもたちも、男の子はサシャを「女の子みたい」とからかい、女の子は「男の子のくせに」と仲間はずれにする。悪気のないその態度の1つひとつは、たしかに強く積極的な攻撃や差別ではないのかもしれない。しかし「ありのままのあなたを決して受け入れない」という態度を何度も何度も積み重ねられたら、当事者はその社会を、小さなサシャにとっては学校やバレエ教室を、自分のいるべき場所だと感じてのびのびとすごせるだろうか。
もう何度も「ありのままの自分を受け入れられなかった」という経験を持つサシャは、微笑を浮かべていてもどこか物寂しげに見える。控えめな表情や言葉からは、傷ついてきた過去があること、そして絶望を感じていることが滲み出ているように思えてならなかった。
しかしこれは海外だけで起きている話でもなければ、ファンタジーでもない。ドキュメンタリーだからこそ観客は、普段多くの人にとって生きてくる中でまったく障壁ではなかった「社会の当たり前」の存在にはじめて気がつくのかもしれない。
見る人が自分が自分らしいと思って選ぶものや色が、誰かに「おかしい、それは受け入れられない」とは言われない側の人だとしたら、それはたまたまであって、そうではない人がいることを知るきっかけになるだろう。そしてそんなたまたまを「自分はそうじゃなかったからよかった」と他人事にせず、サシャのような人が「自分はここにいていいんだ」と思える環境を積極的に育んでいく決意のきっかけにする人もまた、増えるのではないだろうか。
そしてこれは、母と子の物語でもある。
母、カリーヌはサシャの想いや境遇に正面から向き合い、ともに歩む力強いパートナーだ。しかし「母は強し」とか「母の愛は偉大」のような、聞こえのいい言葉で簡単に片付けられるものではない。カリーヌもまた深く傷つき、憤りや不安、罪悪感とともに生きてきた。サシャを含め4人の子育てだけでも気が遠くなるほど大変なはずなのに、サシャとともにいつも足を運び、戦い、心を尽くし、我が子の声を聞こうとする。
自分の子どもがマイノリティだったら、親としてどう接することができるだろう?
この完璧ではない社会で「なるべく生きづらさを感じてほしくない」と思って、よかれと思ってその子どもの本当の気持ちを「気のせいだ」と否定して軌道修正しようとしたり、ちゃんと向き合えず大切にできなかったりする親だって少なくないはずだ。
当事者でも近しい存在である親や兄弟だからこそカミングアウトができなかったり、本当の気持ちを伝えるのは怖いと感じたりする人もいる。サシャもまた、母に心配をかけまいと気丈に振る舞おうとするシーンが描かれていた。そんなことをこんな小さな子どもにさせていいのか?という気持ちでいっぱいになる人もいるだろう。
そんなサシャとカリーヌ、家族のリアルな日々を映した『リトル・ガール』は繰り返しの戦いと葛藤、そしてその先の希望を見せてくれる。
独りでその戦いに勝つことはできないかもしれない。「何をしても変わらない」と諦めたくなるかもしれない。
でも、信頼できる家族がいたら?
本当のことを話せる友達がいたら?
身近に理解者がいたら?
教育機関が変わったら?
私たちは今生きるこの社会で、どんな立場をとるのか。考えさせられる作品となっている。