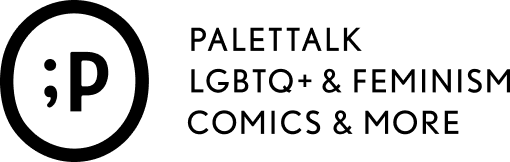トランスジェンダーってなに?よくある誤解と偏見

LGBTQ+について耳にする機会は増えてきたものの、それぞれのセクシュアリティについてきちんと知る機会は、まだまだ多くないのではないでしょうか。
たとえばLGBTQ+のTにあたるトランスジェンダーについて、「トランスジェンダーってこういう人のことかな」となんとなくわかったつもりでいても、「メディアなどで描かれる画一的なイメージをそのまま信じていた」なんてこともあるかもしれません。
この記事では、あらためて「トランスジェンダーとはどんな人を指す言葉か?」という基本的な説明から、よくある疑問、誤解や偏見まで、わかりやすく解説していきます。
トランスジェンダーの定義
トランスジェンダー(Transgender)とは、一般的に出生時に割り当てられた性別と、ジェンダー・アイデンティティ(性自認・性同一性)(*1)が異なる人のことを指す言葉です。
ただし、トランスジェンダーの人のなかには「ジェンダー・アイデンティティ」という概念自体が自分にはしっくりこないと感じている人もいるため、出生時に割り当てられた性別とは異なる性のありようを生きている人という定義が使われることもあります。
一方で、出生時に割り当てられた性別とジェンダー・アイデンティティが一致している人、つまりトランスジェンダーではない人は、シスジェンダー(Cisgender)と呼ばれています。
(*1)「性自認」と「性同一性」はどちらも「ジェンダー・アイデンティティ(Gender Identity)」の訳語であり、それぞれの漢字が持つニュアンスを理由に使いわけられることもありますが、意味は同じです。
「出生時に割り当てられた性別」って?
トランスジェンダーについての説明の中で出てきた「出生時に割り当てられた性別」という言葉には、馴染みのない方も多いかもしれません。
あらためて考えてみると、私たちの暮らす社会では子どもが生まれるとすぐ、必ず男女どちらかのカテゴリーにわけられますよね。
現在の日本の社会システムでは、人が生まれたとき、公的な記録(戸籍など)にその存在が認められると同時に、 性別が登録されることになっています。
医師などが主に生まれた子どもの外性器などを手がかりに、「女の子ですね」「男の子ですね」と判断し、その性別が出生届に記載されます。
そしてこの登録された性別が、その後の人生における様々な公的な手続きや社会的な前提の基盤となるという仕組みになっているのです。
性同一性障害との違いは?
「性同一性障害(Gender Identity Disorder)」という言葉は、かつて医学の分野で使われていた診断名です。2000年代までの日本では、この言葉を通じて「出生時に割り当てられた性別に違和感を抱く人」の存在について社会的な認知が広がりました。
しかし、国際的な診断基準が改訂され、現在は「性別不合(Gender Incongruence)」という名称が用いられています。これは「病気」ではなく、「医療的支援を必要とする状態」として位置づけようという動きの中で見直されたものです。
このように、「性同一性障害」は診断名ですが、「トランスジェンダー」は医療の枠組みによらず当事者が自らをさすための用語、という違いがあります。
トランスジェンダーの中には、手術やホルモン治療などの医療的な措置を望む人もいれば、望まない人もいます。そうした医療的な措置を望むか望まないかによって「本当のトランスジェンダー」であるかが決まるわけではありません。
ノンバイナリーとの違いは?
「ノンバイナリー(Non-Binary)」とは、男女という2つの枠組みにあてはまらないジェンダー・アイデンティティのことを指します。
ここであらためて、一般的なトランスジェンダーの定義を振り返ってみましょう。
トランスジェンダーとは…
出生時に割り当てられた性別と、ジェンダー・アイデンティティ(性自認/性同一性)が異なる人
この定義に照らすと、「女」「男」というどちらの枠組みにもあてはまらないノンバイナリーの人も、広い意味ではトランスジェンダーに含まれるとされています。
ただし、すべてのノンバイナリーの人が自分の性のあり方について「トランスジェンダーである」と捉えているとは限りません。本人がどのようなラベルにしっくりくると感じているのかは人によって異なるため、本人の認識を尊重することが大切です。
また、ノンバイナリーがジェンダー・アイデンティティのあり方を指す言葉であるのに対して、トランスジェンダーは出生時に割り当てられた性別と本人の性自認の関係を表す言葉であることには留意が必要です。
トランスジェンダーに対する誤解や偏見
トランスジェンダーについての認知が広がりつつある一方で、いまだに誤解や偏見も少なくありません。ここでは、そうした誤解について整理しながら見ていきましょう。
「女らしさ/男らしさ」の押し付けがいやだからトランスジェンダーを名乗っているの?
たしかに社会には「女性はこうあるべき」「男性はこう振る舞うべき」といった性別役割の押し付けが存在します。そして多くの人が「そんなルールに縛られたくない」「好きで女性/男性になったわけではない」と感じているかもしれません。
しかし、そうした「性役割に対する抵抗感」と「本人の性自認が何であるか」とは別の話です。
たとえばとある女性が「スカートをはく事を強制されたくない」と考えていたとして、だからといってその人が女性ではない、ということにはなりませんよね。
トランスジェンダーの人は、「女性らしさ・男性らしさという役割が窮屈だから」ではなく、そもそもその前提とされている「あなたはこの性別で、この性別として生きるべきだ」というところに、違和感や、辻褄の合わなさを覚えているといえます。
このように「性別らしさ」に違和感を感じることと、トランスジェンダーであることは、重なり合うことはあっても、必ずしもイコールではないことを覚えておきましょう。
トランスジェンダーの人たちは、ジェンダー規範を強化しているんじゃない?
たしかに、メディアのなかでは「トランスジェンダーの人は女性らしさ・男性らしさに人一倍こだわる」というイメージが繰り返し描かれてきました。しかし、これもトランスジェンダーの当事者に向けられる、よくある誤解のひとつです。
シスジェンダーの人と同じように、トランスジェンダーの人のなかでも、装いや振る舞いの好みは本当にさまざま。長い髪を好む人もいれば、短髪が好きな人もいますし、お化粧が好きな人もいれば、しない人もいます。
つまり、個々人がどんなスタイルを選ぶか、そしてそれが世間で言う「女性らしさ」や「男性らしさ」にどの程度沿っているかは人によって異なるのです。
加えてトランスジェンダーの人は、シスジェンダーの人と同様に、むしろそれ以上に「『その性別らしい』とされる存在であるべきだ」というジェンダー規範の影響を強く受けやすい状況にあります。
なぜなら、そうした規範にある程度沿っていなければ、ミスジェンダリング(*2)などによってアイデンティティを否定されるリスクが高まってしまうからです。
「トランスジェンダーの人たちが規範を強化している」という主張は、このように個々人に「性別らしさ」を求める社会のあり方がトランスジェンダーの人々に規範を押し付けている事実を無視しており、現実に即していないと言えます。
(*2)ミスジェンダリングとは、相手の性自認と異なる性別で呼んだり扱ったりすること。ミスジェンダリングをされた人は、自分の存在が否定され、「いないこと」にされていると感じます。これが日常的に繰り返されると、精神の健康や社会生活を営む能力に悪影響を及ぼすと言われています。
自称すれば簡単に性別を変えられるってこと?それって危険じゃない?
「ジェンダー・アイデンティティ」の訳語として使われている「性自認」という言葉に「自認」という語が含まれていることから、「一時の思いつきで名乗れば、性別を変えられる」というような誤解を抱いてしまっている人もいるかもしれません。
けれども「性自認」が指しているのは、一時の気分や思いつきではありません。「自分はどの性として生きているのか」「どの性として生きていくことに、整合性が取れていると感じるのか」という、一定程度継続的な、本人の内側に深くある感覚に基づくものです。
トランスジェンダーの人が、自由気ままに性別を選んでいるという理解は、大きな誤りなのです。
加えて、実際に日本で法律上の性別を変更するには、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(特例法)」に基づく家庭裁判所での審判が必要です。そこでは、以下のような厳しい条件が定められています。
- 18歳以上であること
- 現に婚姻していないこと
- 現に未成年の子どもがいないこと
- 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
- その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。(*3)
参考:https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0100000111
このように、法律上の性別変更は「思いつきの自称」でできるような簡単なものではなく、身体的・社会的・法的なハードルが非常に高いのが現状です。
(*3)現時点で4つ目の生殖不能の手術要件については違憲判決が下されており、5つ目の外観要件についても「違憲の事態が生じ得る」との判断が下されています。
さいごに
トランスジェンダーの人々と実際に接する機会がほとんどないなかで、メディアの断片的な情報やインターネット上の噂話にいつでも触れられる状況は、今回の記事で紹介したようなさまざまな誤解が広がる可能性を高めてしまいます。
だからこそ、当事者の声に耳を傾け、正しい情報を知ることが、誰もが安心して生きられる社会への第一歩になるのではないでしょうか。
参考文献・リンク
・周司あきら・高井ゆと里(2023)『トランスジェンダー入門』集英社.
・周司あきら・高井ゆと里(2024)『トランスジェンダーQ&A 素朴な疑問が浮かんだら』青弓社.
・https://trans101.jp/
・https://www.health.harvard.edu/blog/misgendering-what-it-is-and-why-it-matters-202107232553