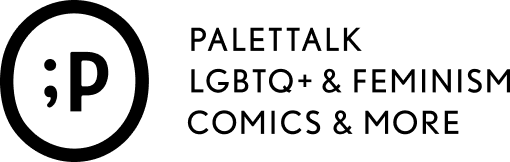それ、もしかして「マイクロアグレッション」かも?

「そんなつもりじゃなかったのに…」「軽い冗談のつもりだったのに、相手を傷つけてしまったかもしれない」。職場でふと耳にする、あるいは自分自身が言ってしまったかもしれない、そんな些細な言動。もしかしたら、それは「マイクロアグレッション」かもしれません。
マイクロアグレッションとは、差別的な意図がなくとも無意識のうちに特定のマイノリティ(少数派)の人々を傷つけ、疎外感を与える言動のことです。
些細で気づかれにくいからこそ、その影響は深く、職場の心理的安全性を損なう大きな要因となってしまいます。
「悪意がなかったとしても傷つけてしまう」
「誰かの心理的安全性を知らず知らずのうちにおびやかしてしまう」
なくしていくことが難しいマイクロアグレッションだからこそ、あらためてその意味や具体例、対策について考えていきましょう。
職場でよくあるマイクロアグレッションの例
マイクロアグレッションは、日常のさまざまな場面で起こりえます。ここでは、特に職場で起こりやすい例をいくつかご紹介します。
1. LGBTQ+に関するマイクロアグレッション
- 「(カミングアウトされた際に)私は気にしないよ」
安心させようとするつもりの言葉ですが、この表現には「本来なら気にするべきことだけれど、自分は特別に受け入れる」というニュアンスが含まれてしまうことがあります。
カミングアウトは、その人にとって大きな勇気を必要とする行為です。その気持ちを尊重し、より心理的安全性の高い関係性をつくるためには、まずは前提の無意識の偏見に気づくことが大切です。
- 「LGBTQ+って今どきだね!」
「今どき」という言葉には、流行や一時的なブームのようなニュアンスが含まれています。しかし、LGBTQ+は一過性のトレンドではなく、人が本来持っている多様な性のあり方を指すものです。
この表現は、相手の存在を軽視したり、「特別なこと」として周囲から切り離す印象を与えてしまう可能性があります。
- 「彼氏/彼女はいるの?」と決めつける
職場の同僚と、プライベートな話題になることはめずらしくありません。たとえば恋愛の話題をするときに「彼氏はいるの?」「彼女はいるの?」と尋ねることには、「恋愛対象は異性である」という前提が含まれています。
そのため、同性愛者やバイセクシュアルの人にとっては、自分の存在が見えていない、無視されていると感じることがあります。意識せずにかけた言葉が、相手に「自分はここに居場所がないのかもしれない」という孤立感を与えてしまう場合があるのです。
- 「さすがゲイの人はセンスがあるね」
一見すると褒め言葉のように聞こえるかもしれませんが、このような発言には「ゲイだからセンスがある」という固定的なイメージ(ステレオタイプ)が含まれています。
実際には、センスや趣味嗜好は性的指向とは関係がなく、1人ひとり異なるものです。このような言い方は、相手を「個人」として見るのではなく、「ゲイ」という属性で一括りにして評価してしまうことにつながります。
結果的に「自分の個性ではなく、性的指向で判断されている」と感じ、居心地の悪さを与える場合があります。褒めるときは、その人自身の特徴や魅力に目を向けることが大切です。
2. 女性やジェンダーに関するマイクロアグレッション
- 「女性なのに理系なんだ、すごいね」
この言葉は一見すると褒めているように思えますが、「理系は男性の分野であり、女性は珍しい」という固定観念が前提にあります。そのため「女性の能力は低いのが普通」という暗黙のメッセージになってしまい、本人にとっては自分の努力や実力が正当に評価されていないと感じることにつながります。
性別と能力を結びつけるのではなく、その人自身の取り組みや成果に焦点をあてて伝えることが大切です。
- 「子育てがあるから無理しなくていいよ」
一見「配慮」のように聞こえる言葉ですが、「子育てをしている=仕事での挑戦やキャリアアップはできない」という決めつけを含んでいます。
その結果、本人が望む可能性を狭めてしまい、やる気や自信を奪うことになりかねません。子育てをしているかどうかに関わらず、1人ひとりの希望や状況を尊重し、本人の意思を確認したうえでサポートする姿勢が大切です。
- 「女性ならではの感性だね」
一見すると相手を評価している褒め言葉に聞こえますが、この表現には「感性=女性特有のもの」という決めつけが含まれています。その結果「男性には感性がない」「女性は感性で勝負する」といった固定観念を強めてしまう危険性があります。
人の発想や感性は性別ではなく、その人の経験や価値観から生まれるものであり、個性として尊重されるべきものです。褒めるときは「あなたの感性」「あなたのアイデア」と、性別を持ち出さず個人に焦点を当てることが大切です。
3. その他のマイクロアグレッション
- 「障がいがあるのに、こんなこともできるんだ!」
この言葉は驚きや称賛を表しているつもりでも、「障がいがある人は何もできない」という低い期待を前提にしています。そのため、本人にとっては「自分の力を正当に評価されていない」と感じたり、「障がい=できない人」という偏見を強化してしまう可能性があります。
- 「日本語上手ですね!」
本人が長年日本に住んでいたり、日本語を日常的に使っている場合でも、繰り返し「上手ですね」と言われるといつまでも「あなたは外から来た人」という線引きをされているように感じることがあります。
また、いわゆる「日本人」という言葉からイメージされる見た目とは違う人だったとしても、その人がどのような言語環境で生活してきたかを決めつけることはできません。
これらの言動は、発言者には悪気がなくとも、受け取った側は「自分はこの職場で異質な存在なのかもしれない」「能力を正当に評価されていない」と感じ、孤立感や不信感を抱くことにつながります。
なぜマイクロアグレッションは問題なの?
「小さい攻撃性」と訳されるマイクロアグレッションですが、職場にもたらす影響はけっして小さいものではありません。
- 心理的安全性の低下: 心理的安全性が低下すると「どうせ言っても理解されない」「自分の声は尊重されない」と感じる従業員が増え、その結果、自由に意見を言うことが難しく、新しいアイデアも生まれにくい職場になってしまいます。
- エンゲージメントの低下: 「自分は尊重されていない」と感じると、仕事へのやる気や会社への貢献意欲が下がってしまいます。
- 離職率の増加: 居心地の悪さや不公平感を原因に、優秀な人材が離職してしまうリスクが高まります。
- ハラスメントの温床: 些細なマイクロアグレッションが放置されることで、より深刻なハラスメントに発展してしまう可能性もあります。
マイクロアグレッション対策の具体的なステップ
マイクロアグレッションを防ぎ、誰もが安心して働ける職場を作るためには、社員1人ひとりの意識と行動を変えることが不可欠です。
この章でご紹介する具体的なダイバーシティ推進施策の例を、LGBT研修・施策の企画に役立てていただけると幸いです。
1. 意識を高め、知識を身につける
まずは「マイクロアグレッションとは何か」「なぜ問題なのか」を全員が理解することが第一歩です。
- 専門家による講演・ワークショップ
外部の専門家を招き、具体的な事例を交えて学ぶ場を設けます。ワークショップ形式で「どんな言動がマイクロアグレッションになるか」「どう言い換えられるか」を考えることで、理解が深まります。 - 社内報での継続的な啓発
定期的に記事を掲載し、具体例や改善のヒントを共有することで、関心を持ち続けてもらいます。
LGBT研修や施策の種類についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
2. 「自分ごと」として考えるための教材活用
長年にわたりLGBTQ+に関する発信を続けてきたPALETTALKが提供するマンガ教材は、企業における具体的なシチュエーションを多数収録しています。共感を呼ぶストーリーと、実際の行動に繋がる実践的な内容で、より深く理解を進めることができます。
- マンガ教材の活用
LGBTQ+やジェンダーをテーマにした教材を使い、ストーリーを通して事例を学びます。登場人物の気持ちに触れることで「自分も無意識にやっていたかもしれない」と気づき、行動の変化につながります。- 「SOGIとは?」「無意識の偏見とは?」などの基礎知識をマンガでわかりやすく学ぶことができます。
- 「カミングアウトへの対応」「トランスジェンダーへの配慮」など実践的な内容も当事者の声に寄り添いながら理解を深められます。
- 「SOGIとは?」「無意識の偏見とは?」などの基礎知識をマンガでわかりやすく学ぶことができます。
- オリジナル教材の制作
貴社の職場で実際に起こりうるケースをマンガ化することも可能です。- 「自分の会社のことだ」と強く意識しやすい
- セミナー内容をマンガにすることで研修内容を復習できる
- ポスターにして掲示することで、常に意識を喚起できる
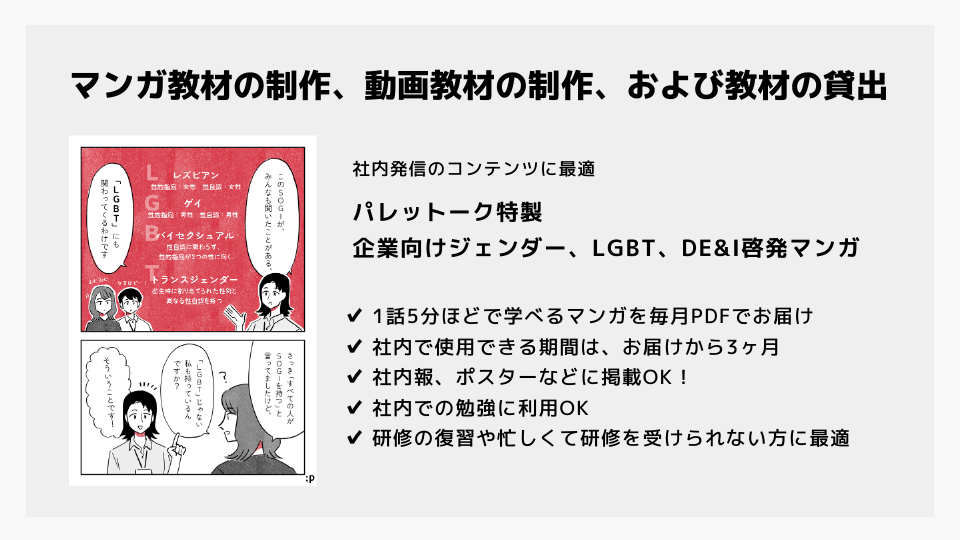
3. 相談窓口の設置と再発防止
万が一、マイクロアグレッションが発生してしまった場合の相談窓口を明確にし、安心して相談できる環境を整えることも重要です。相談内容を真摯に受け止め、適切な対応をすることで、再発防止と信頼関係の構築につながります。
ダイバーシティ施策に困ったときは?
私たち「パレットーク」は、誰もが安心して、自分らしく働ける職場づくりをサポートします。
マイクロアグレッションへの対策は、一度で完了するものではなく、継続的な取り組みが求められます。マイクロアグレッションに関する研修やマンガ教材の提供、オリジナルのマンガ制作など、貴社の状況に合わせた柔軟なご提案が可能です。
より具体的な制度設計やトラブル時の対応、社外への情報発信、あるいは「マイクロアグレッション」のような専門用語について詳しく知りたい場合は、お気軽にご相談ください。貴社の職場をよりよい場所に変えていくお手伝いができれば幸いです。