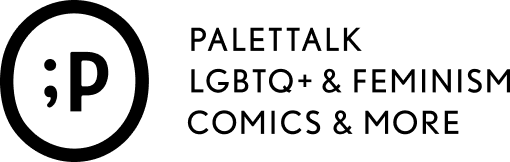その一言、相手を傷つけてない?LGBTQ+と日常会話
「LGBTQ+」という言葉が、日本社会でもここ数年で一気に広がってきました。SNSやメディアを通じて、「いろんな人がいる」「誰もが自分らしく」という言葉を目にするようになったのも、たしかに社会の変化の表れだと言えるでしょう。
でも、その変化の中で「よかれと思って」かけた言葉や、「理解しているつもり」の対応が、実は誰かを深く傷つけていることもあります。
今回の記事では、Xジェンダーの主人公が、美容院で実際に体験したエピソードを通じて、一見“歓迎”や“理解”に見える言動の背景に潜む問題について考えてみたいと思います。
その言葉、本当に大丈夫?
今回紹介したマンガでは、美容師が主人公にこう話しかける場面があります。
「トランスなんちゃらですか?」「 “ホモ”っぽい人も来ましたよ!」
希望する髪型を本人が語っていないセクシュアリティと結びつけ、それを周囲にも聞こえる声で語る様子に主人公はショックを受け、心がざわつきます。
髪型や服装などの外見だけでその人のセクシュアリティを判断するのは、避けるべき行動です。それはあくまで「その人の表現」であって、「好きになる相手」や「生まれたときに割り振られた性別と性自認の関係」との間に絶対的な関係はありません。
また私たちが日常的に使う言葉には、それぞれ語源や使われてきた歴史的な背景があります。たとえば「ホモ」「レズ」「オカマ」といった言葉は、かつて侮蔑的に使われてきた経緯があり、避けるべき表現とされています。
たしかに当事者の中には、これらの言葉を自称として使う方もいます。また、当事者のコミュニティ内では親しみを込めて互いに使われることがあるのも事実です。
しかし、ある人がその言葉に対して嫌な気持ちにならなかったとしても、他の人も同じように感じるかと言えば、そうとは限りません。実際に第三者から「レズ」や「ホモ」と呼ばれて嫌な気持ちになる当事者も多くいます。
相手のセクシュアリティを決めつけてしまうのはもちろん、「理解あるつもり」でかけた一言が、かえって相手に「この人には何を言われるかわからない」という不安を抱かせてしまうこともあります。だからこそ、「その表現、大丈夫かな?」と一度立ち止まって考えることが大切です。
「自分は平気」とわかったつもりにならないために
「俺、そういうの理解あるんで大丈夫です!」
美容師が発したこの言葉のように「自分には特定のマイノリティの友人や知人がいるので、自分は差別をしていない」とする主張を見かけたことのある人も多いのではないでしょうか。一見寛容な姿勢を示しているように聞こえますが、実はこの考えにも注意が必要です。
ある人が特定のマイノリティ性を持つ誰かと親しくしていたとしても、その人が相手の経験や痛みに対して深く理解できているとは限りません。
「自分は絶対に差別しない人間だ」と決めつけてしまうと、自身の中にあるかもしれない無意識の偏見や、過去の言動を振り返る機会を逃してしまうおそれがあります。
その結果として、当事者が感じた違和感や傷つきに対して「その反応は過敏すぎる」「気にしすぎではないか」といった形で片づけてしまうことにもつながりかねません。また、「差別ではない」「悪意はなかった」と言い切ってしまうことで、相手が実際に感じた傷つきや違和感を「なかったこと」として扱ってしまう危険性があります。
「自分は絶対に差別しない」とは誰もが言い切れませんが、差別に反対することはできます。つねに「どう受け取られたか」にも耳を傾け、対話を重ねていくことが大切なのではないでしょうか。
「何も言えなくなる」不安について
「そんなこと言ったら、何も言えなくなっちゃうじゃん」
「どう接したらいいのかわからないよ」
そう感じたことがある人もいるかもしれません。
悪気はなかったのに相手を傷つけてしまったり、「配慮のつもり」がうまく伝わらなかったりした経験があると、次は何を言えばいいのか迷ってしまうのも自然なことです。
しかし本当に大切なのは「正しい言葉を完璧に使うこと」ではなく、その都度「相手がどう受け取ったか」に目を向けることなのではないでしょうか。
- もし相手が少し戸惑っていたら、「ごめん、何か気になることがあったら教えてね」と声をかけてみる。
- わからないことがあれば「教えてもらえると嬉しい」と丁寧に聞いてみる。
完璧を目指すよりも、それぞれの関係の中で少しずつ言葉を選び直していけることの方が、ずっと大きな安心感につながるはずです。「何も言えなくなる」ではなく、「どう言えば安心につながるか」を一緒に探していくことで、誰もが心地よくいられる関係性を築くことができるのではないでしょうか。
さいごに
「LGBTQ+」という言葉や、それに関する言葉、当事者の存在が少しずつ知られるようになってきた昨今。それ自体はとても大切なことですが、言葉が広まるだけでは偏見がなくならないのかも…と考えさせられるのが、今回のエピソードです。
無意識のうちに相手の性を決めつけたり、話のネタとして強調したりする場面は残念ながらまだ多く残っています。
また「よくわからないけど、重くならないようにしよう」という空気の中で、使わないことが望ましい言葉を使ってしまったり、当事者が傷つくことも少なくありません。
多くの人が当事者の現状を理解し、社会制度を考えるためには、さらに多くの可視化が必要です。
言葉だけでなく、その背景や当事者の困りごとなどを知るためにも、この機会に、一緒に学び、考えてみませんか?