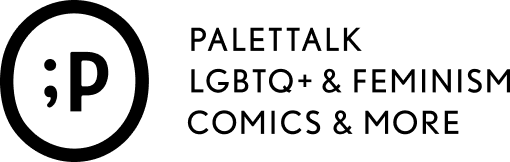ノンバイナリーってなに?従来の 「男か女のどちらか」に当てはまらない性のあり方について
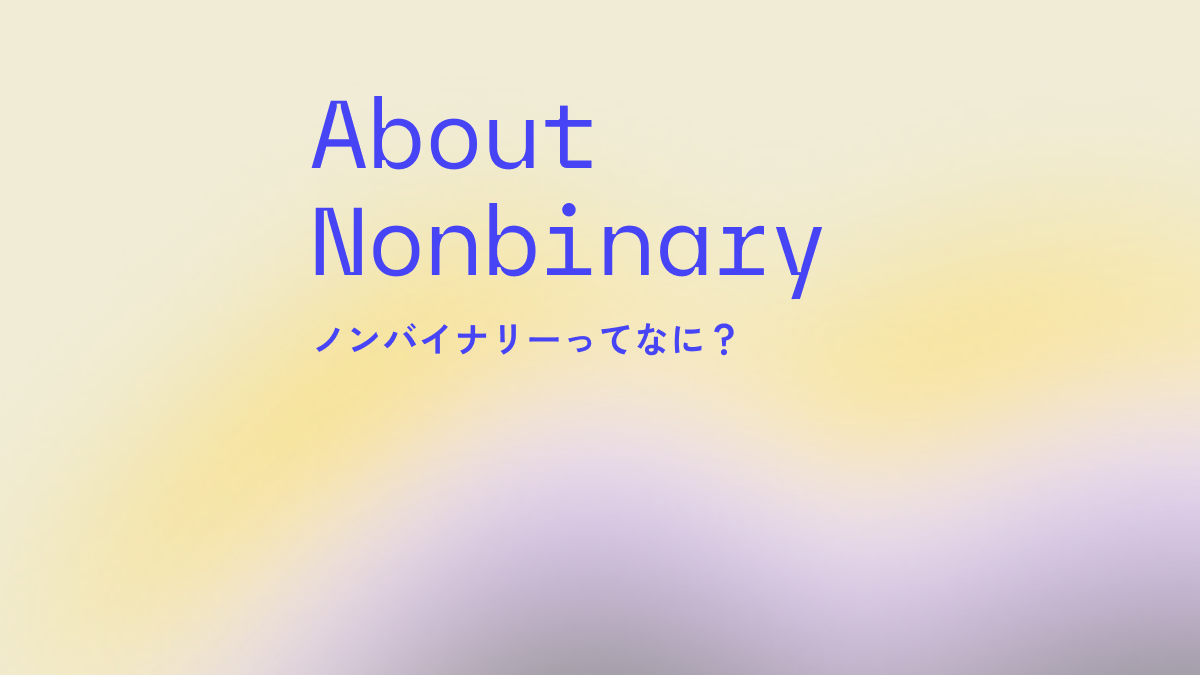
皆さんは、ノンバイナリーという言葉を知っていますか?
ノンバイナリーとは、「男・女という従来の二元的な枠組みに当てはまらない性自認」を指します。とはいえ、この文言を聞いただけではピンとこない方も多いかもしれません。
パレットークではノンバイナリーについてマンガで発信することも多いですが、今回はあらためて「ノンバイナリーってどんな性のあり方のこと?」ということについてまとめていきたいと思います。
性別二元論(ジェンダー・バイナリー)とノンバイナリーの関係
「ノンバイナリー(Non-Binary)」とは、男女という2つの枠組みにあてはまらない性自認(ジェンダー・アイデンティティ)のことを指します。出生時に割り当てられた性別に関わらず「自分は男でも女でもない」と感じる人たちがいます。ここ数年で少しずつ知られるようになってきましたが、まだ社会の中で十分に理解されているとは言えません。
ノンバイナリーを理解するためには、まず「性別二元論(ジェンダー・バイナリー)」という考え方を知る必要があります。
バイナリー(Binary)とは、「2つの項を持つ」という意味の英単語。ジェンダーに関しては、「男女の2つの項を前提とする」という意味で使われます。
性別二元論は男女二元論とも言われるように、「性のあり方は男か女のどちらかである」とする考え方です。この考え方に基づいて、私たちは日常生活でも法律上でも、男女のどちらかの枠に振りわけられています。
男か女のどちらかに振りわけられるとき、その根拠となる要素は場合によって様々です。法律上は「出生時に割り当てられた性別」や「戸籍の性別」に基づいて男女のどちらかに振りわけられることが多いですが、それだけではありません。
たとえば、
- どんな服装をしているのか?メイクをしているか?
- 言葉遣いや仕草、態度
といった要素からも、私たちは男女のどちらかだと判断されます。日常生活においては、身分証を常に提示するわけではないので、むしろ「戸籍上の性別」よりもこうした「振る舞いや外見」などから判断される方が多いかもしれません。
トランスジェンダーとノンバイナリーの違いは?
ノンバイナリーの性のあり方について読んでいて、「トランスジェンダーとの違いはなんだろう?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。
トランスジェンダーとは、「生まれたときに割り当てられた性別とは異なる性のあり方で生きる/生きようとする人」のことを指す言葉です。
そして広い意味では、ノンバイナリーも広義のトランスジェンダーと捉えられます。
しかし狭義のトランスジェンダーはほとんどの場合、性別二元論を前提としています。たとえば、トランスジェンダー男性は出生時に割り当てられた性別は女性ですが、男性として生きる/生きようとする人のこと。あくまで彼らは男性です。逆に、トランスジェンダー女性は出生時に割り当てられた性別は男性ですが、女性として生きる/生きようとする人のことなので、彼女たちは女性です。
どちらも性自認が男女のどちらかとなるので、ノンバイナリーの「男女のどちらでもない」という性自認とは異なります。
Xジェンダーとノンバイナリーの違いは?
最近はXジェンダーという性のあり方も少しずつ知られてきました。パレットークでもこれまでXジェンダーに関するマンガを発信してきましたが、実はこのXジェンダーは日本語独自の表現で、ノンバイナリーと重なる部分もありつつ、完全に同じ意味というわけではありません。
Xジェンダーは、
- 両性 (自分は男女のどちらでもあると感じる)
- 中性(自分は男女のまんなかであると感じる)
- 無性(自分に性別はないと感じる)
- 不定性(性自認が定まっていない)
などにわけることができ、Xジェンダーとノンバイナリーは「既存の男女の枠には当てはまらない」という意味で共通点があります。しかし、たとえばXジェンダーの両性と中性は「男女」という枠組みを前提として捉えられる場合が多いので、その点でノンバイナリーとは異なる、とも言うことができます。
ノンバイナリーは、「性のあり方を性別二元論で捉えない」という点にアクセントがあると言えるかもしれません。
とはいえXジェンダーの捉え方が様々であるのと同様に、ノンバイナリーの捉え方も様々で、人によってどの名称や定義がしっくりくるかは異なります。ノンバイナリーの人であっても、「男女のどちらでもある」「中間である」と感じる人はいますし、身体への違和感を持ち医療措置を必要とする人もいれば、そうではない人もいます。
大切なのはどんな性のあり方を持っていても、相手のことを勝手に決めつけずに尊重することなのではないでしょうか。
ノンバイナリーの人が抱える困難の例
このように社会の多くの場面でまだまだ性別二元論が前提となっているため、ノンバイナリーの人々はしばしば「どちらかに振り分けられる」ことを強いられてしまいます。本人が「自分は男でも女でもない」と感じているにもかかわらず、外見や振る舞い、制度上の理由から一方的にどちらかに決めつけられてしまうことがあるのです。
日常的な「男女二択」への強制
- アンケートや登録フォームで性別を「男・女」からしか選べない
- トイレや更衣室が男女でしか区分されていない
呼称や敬称の扱い
- 「〇〇君」「〇〇さん(女性らしい扱い)」など、性別前提の呼び方をされて違和感を覚える
- 「彼/彼女」など、性自認に沿わない人称代名詞で呼ばれる
戸籍や法制度の制約
- 日本では法的に「男性」「女性」以外の性別が認められていないため、身分証明書や公的手続きで無理にどちらかを選ばなければいけない
社会的な誤解や偏見
- 「結局どっちなの?」「中途半端」などといった無理解な発言を受ける
- ノンバイナリーであること自体を「存在しない」「気のせい」と否定されることがある
日常生活の小さなストレスの積み重ね
- 就職活動や職場で性別に基づいたドレスコードや制服が求められ、自己表現が制限される
- 服装や仕草に対して「男らしくない」「女らしくない」とコメントされる
このように社会が「男女の二択」を当然の前提とする限り、ノンバイナリーの人々が日常生活や制度の中で直面する困難は続いてしまうのです。
ノンバイナリーに関するよくある誤解と偏見
より深くノンバイナリーについて理解を深めるために、ノンバイナリーに対するよくある誤解や偏見を見ていきましょう。
「結局どっちか(男か女)なんでしょ?」
ノンバイナリーの人に対して最も多い誤解のひとつが、「結局は男か女のどちらかに当てはまるはず」という見方です。
私たちの社会は、性別を「男性か女性か」という二分法で捉える仕組みに基づいてきました。そのため「2つの枠に収まらない」という感覚が理解されにくいのです。
しかし、ノンバイナリーは「中間」や「どちらでもない」といった単純な分類ではなく、男女の二項対立を前提としない多様なあり方を含んでいます。つまり「男か女か」という問いそのものがノンバイナリーにとっては的外れなのです。
こうした誤解は「枠にはめる」圧力となり、当事者の尊厳を傷つける言動ですので、注意が必要です。
「ノンバイナリーはただの流行/一時的な気持ち」
「ノンバイナリーは最近できた言葉だから、流行や一時的なブームにすぎない」と捉えられる場面もまだまだ多くあります。しかし、ノンバイナリーというあり方自体は近年突然生まれたものではなく、歴史的にも文化的にもさまざまな社会に存在してきました。
そもそも性のあり方は流動的で、移り変わる可能性は誰にとってもあります。しかしだからといって、誰かの性のあり方を「一時的」と決めつけることは、その人の自己認識を否定する行為にあたり、とても傷つけるもの。
ノンバイナリーという性自認は、たしかに存在し、認められるべき性のあり方なのです。
「はっきりしていない=優柔不断ってこと?」
ノンバイナリーの人に対して「男でも女でもないなんて、はっきりしていなくて優柔不断なのでは?」という見方をされることがあります。しかし、これは大きな誤解です。ノンバイナリーは「決められない」のではなく「どちらにも当てはまらない」という明確な自己認識に基づいています。
私たちの生きる社会は「男か女か」を前提としているので、「決断を避けている」ように捉えられることもあるかもしれませんが、むしろ自分自身のアイデンティティを「あたりまえ」に委ねない姿勢は、非常に強い意志の表れとも言えるのではないでしょうか。
「恋愛や性的指向と混同される」
ノンバイナリーは性自認、つまり「自分をどう認識するか」に関わる概念です。
しかしまだまだ性のあり方について理解が進んでいない社会では、「同性愛なの?異性愛なの?」といった恋愛対象や性的指向と混同されがちです。
実際には、ノンバイナリーを自認する人のあいだでも様々な性的指向・恋愛的指向を持つ人がおり、それぞれがたしかな性のあり方です。
性自認(ノンバイナリーかどうか)と性的指向(誰を好きになるか)は、性のあり方の異なる側面に関わっているので、「自分をどう認識するか」と「誰に惹かれるか」をわけて考える必要があります。
「ファッションの好みの問題なのでは?」
外見的なスタイルやファッションが男女のイメージに結びつけられることから、「ノンバイナリーって結局は中性的な服を着たい人でしょ?」と誤解されることがあります。しかし、ノンバイナリーは単なる服装の好みではなく、自分自身のジェンダー・アイデンティティに関わるものです。
中性的な服装を好む人すべてがノンバイナリーではありませんし、ノンバイナリーの人が必ずしも中性的な服を選ぶわけでもありません。ファッションはあくまで表現方法のひとつであり、内面的な自己認識とイコールではないのです。
服装と性自認を混同するのは当事者を矮小化する見方につながります。
知ることで可視化される性の多様性
比較的新しい性のあり方とされるノンバイナリーですが、「ノンバイナリーの人が最近になって突然世界に現れた」ということではもちろんありません。ノンバイナリーという性のあり方を持つ人はずっと昔からいましたが、その名称が最近知られるようになり、その存在が可視化されてきたというだけのことです。
よく耳に新しいセクシュアリティやジェンダー・アイデンティティの名前が出てくると「カテゴリーを増やすだけでは、かえって人々の性のあり方を限定してしまうのではないか?」という疑問が投げかけられることがあります。もしくは「セクシュアリティやジェンダー・アイデンティティに細かく名前を付けていくことに意味があるの?」という疑問もあると思います。
しかし今の社会は、性別二元論や異性愛などが当然視され、当たり前にシステムや人々の認識の前提となっています。そんな中で、「既存の性のあり方に当てはまらない人々」は、不可視化され「いないこと」にされがちです。
また社会の中であまりにも当たり前とされてきた性のあり方の中で、「自分は普通とは違っている」「自分の存在はなんなんだろう」と言語化できずに苦しんでいる人はたくさんいます。そして、自分の性のあり方としっくりくる名前を見つけて安心したり、同じ性のあり方を持つ仲間と出会って安心したり、逆に「自分とは微妙に違うな」という感覚からさらに自分の性のあり方が言語化できる人もいます。
このような経験は「意味がない」と軽視していいことではありません。どんな性のあり方を持っていようと、その人の存在をないことにしない/抑圧しないためには、名前が知られる必要があるのです。
大切なのは、「名前を増やすこと/見つけること」それ自体ではなく、
- 知ることで自分の性のあり方を見つめるきっかけになる
- 自分の当たり前を誰かに押しつけないようになる
- 社会で「ないこと」にされている人を減らしていく
ということなのではないでしょうか。
性のあり方は今も昔も多様でしたが、それが知られるようになったのは最近のこと。そしてまだまだ「当たり前」の性のあり方につらい思いをしている人は多くいます。
性別二元論を前提としたジェンダー・アイデンティティを持っている人にとって、「ノンバイナリーであること」の感覚を完全に理解することは難しいかもしれませんが、理解しなければその人のことを尊重できないというわけではありません。そして「理解できない」ということは「知らなくてもいい」と同じでもありません。
ノンバイナリーという性のあり方を知る人が増えることによって、世の中の当たり前を問い直し、誰かの存在をいないことにしないシステムへアップデートしていく必要があるのではないでしょうか。